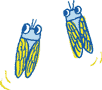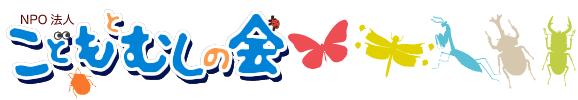NPO法人こどもとむしの会
感動! セミの羽化
夏の夜は、セミの羽化を見よう!
それはそれは感動的な、小さないのちの営みです。どんな大都会でも、かんたんに見ることができますよ。
まだ見たことのない人は、ぜひチャレンジしてみてください。

公園での羽化の観察
2010年8月3日 東京都港区有栖川宮記念公園(上の写真も)セミの幼虫は、夕方、地面から出てきて、夜のうちに最後の脱皮(羽化)をして、セミになります。ぬけがらはよく目にしますが、羽化は夜に行われるので、見たことのない人は意外に多いです。
夜の公園には危険もあります。何人かのグループで観察すると、楽しいですよ。
 |
夕方、セミが鳴いているうちに現地に行って、どんなところにセミがいそうか、よく観察しておきます。「ぬけがらさがしペナントレース」をすると、セミがどんなところで羽化しているのか、よくわかります。地面から出てきた幼虫も、みつかるでしょう。 |
 |
セミの幼虫が、ちょうど、穴から出てくるところです。小さな穴を見つけたら、中に幼虫がいるかもしれません。指でつついてみましょう。 |
 |
日が暮れて暗くなると、公園のあちこちで、セミが羽化をはじめます。夜7時半〜8時頃には、たくさん見られます。 |
 |
こどもたちだけでなく、ママたちにも、とても喜ばれます。 「光る腕輪」は、夜の観察会での楽しいアイテムです。迷子になるのを防ぐことができます。 |
室内での羽化の観察
2010年7月23〜24日 兵庫県香美町ハチ北高原幼虫をカーテンや網戸にとまらせると、しばらくはうろうろしていますが、やがて落ち着いて、羽化をはじめます。
これは、アカエゾゼミの羽化のようすです。羽化の時刻が夜遅いですが、これは、幼虫がカーテンを気に入らず、何度も落ちたり、放浪したからだと思います。
 |
 背中が割れました。 |
 |
 ニョキニョキと、セミが出てきました。 |
 |
 脚(あし)が出ました。体は、だんだん、うしろに、そりかえっていきます。 白い「ひも」のようなものが見えます。 |
 |
 逆さ吊りになりました。おっこちそうです。 しばらく、脚がかたまるのを待っています。 |
 |
 翅(はね)が大きくなってきています。 少しずつ起き上がります。 |
 |
 起き上がりました。 いちばんの見せどころです。 |
 |
 腹をぬいて、ぬけがらにぶら下がりました。 あとは、翅を伸ばすだけです。 |
 |
 だいぶ翅が伸びました。 |
 |
 ほぼ、翅が伸びました。 |
 |
 水平に開いていた翅を、屋根型にたたみました。 体や翅のもようは、まだぼんやりしています。 |
 |
 朝になりました。体や翅のもようもはっきりしてきました。もう、飛ぶことができます。 |
 |
ぬけがらだけが、残りました。 |
 |
撮影しているところ。ハチ北高原サマースクールでの一幕です。 このように、土から出てきて歩いている幼虫を見つけたら、室内のカーテンなどにとまらせて、じっくり観察できます。 |
ぬけがらの、白い「ひも」について
  |
ぬけがらの裂け目から出ている白い「ひも」のようなものは、幼虫時代の「気管」のぬけがらです。白い「ひも」は、よく見ると、胸と腹にある「気門」という穴からつながっています。昆虫には肺がないので、「気門」という空気穴から、「気管」という管を使って、体の中に空気を運びます。 |